 偼丆Cor侾傛傝惉棫
偼丆Cor侾傛傝惉棫佀偵偮偄偰帵偡丅俙亖倣俤偺偲偒丆冇A(倶)亖倶亅倣丆倖A(倶)亖(倶亅倣)2傛傝惉棫
丂丂俙亗倣俤偺偲偒丆冇A(倶)亖倖A(倶) 傛傝惉棫偡傞丅丂丂丂仩
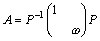 偲峔惉偱偒傞丅偙傟偑丆夝偺堦斒宍偱偁傞丅
偲峔惉偱偒傞丅偙傟偑丆夝偺堦斒宍偱偁傞丅
 偑梌偊傜傟偨偲偡傞丅
偑梌偊傜傟偨偲偡傞丅
Prop俀亅侾丏乮Caylay-Hamilton偺掕棟乯
丂俙偵懳偟偰丆俙2亅(倎亄倓)俙亄(倎倓亅倐們)俤亖俷 偑惉棫偡傞丅
埲屻丆
丂丂丂倖A(俙)佭俙2亅(倎亄倓)俙亄(倎倓亅倐們)俤亖俷丂丂丂乮俀丏侾乯
丂丂丂倖A(倶)佭倶2亅(倎亄倓)倶亄(倎倓亅倐們)
偲昞偡丅倖A(倶)亖倶2亅(倎亄倓)倶亄(倎倓亅倐們)亖侽 偺俀偮偺夝傪 兛丆兝偲偡傞偲
丂丂丂倖A(倶)亖(倶亅兛)(倶亅兝)丆倖A(俙)亖(俙亅兛俤)(俙亅兝俤)丂丂丂乮俀丏俀乯
偙偙偱丆夝偲學悢偺娭學傛傝丆兛亄兝亖倎亄倓丆兛兝亖倎倓亅倐們
丂丂丂倖A(俙)亖俙2亅(倎亄倓)俙亄(倎倓亅倐們)俤亖(俙亅兛俤)(俙亅兝俤)亖俷丂丂丂乮俀丏俁乯
傪Caylay-Hamilton偺曽掱幃乮埲壓丆俠俫俤偲棯徧乯偲偄偆丅傑偲傔傞偲丆
Prop俀亅俀丏俙偺屌桳抣偑丆兛丆兝佀俠俫俤丂倖A(俙)亖(俙亅兛俤)(俙亅兝俤)亖俷偑惉棫
丂偟偐偟丆偙偺媡偼惉棫偟側偄丅乮斀椺丗俙亖兛俤偺偲偒乯
丂傑偨丆倗(俙)亖俷偲側傞擟堄偺俙偺懡崁幃倗(俙)偵偮偄偰丆倗(倶)偼倖A(倶)偱妱傝愗傟傞偲偼尷傜側偄丅
乮斀椺丗俙亖俤偺偲偒丆倖A(倶)亖(倶亅侾)2丆倗(俙)佭俙亅俤偲偍偔偲丆倗(倶)亖倶亅侾乯
丂偦偙偱丆倗(俙)亖俷偲側傞擟堄偺俙偺懡崁幃倗(俙)偵偮偄偰丆倗(倶)傪妱傝愗傟傞懡崁幃傪掕媊偡傞丅
Def俀亅俁丏 乮嵟彫懡崁幃乯俙偵懳偟偰丆師偺傛偆側俙偺懡崁幃冇A(俙)傪掕媊偡傞丅
丂丂丂俙亖倣俤偺偲偒丆冇A(俙)佭俙亅倣俤丆俙亗倣俤偺偲偒丆冇A(俙)佭倖A(俙)
丂偙偺冇A(俙)偼堦堄揑偵懚嵼偟丆deg冇A亝俀偱偁傞丅偙偺冇A(俙)傪俙偺嵟彫懡崁幃偲偄偆丅 乮俀師偺惓曽峴楍偵偮偄偰偼丆偙偺掕媊偱嵟彫懡崁幃偺懚嵼偲堦堄惈偑柧傜偐偱偁傞乯
Prop俀亅係丏倗(俙)亖俷佀倗(倶)偼冇A(倶)偱妱傝愗傟傞丅
pr乯
俠俙俽俤侾丗俙亖倣俤偺偲偒丆冇A乭(倶)亖倶亅倣丆
丂丂倗(俙)亖俷傛傝倗(倣俤)亖俷丆倗(倣)俤亖俷丆倗(倣)亖侽
丂丂傛偭偰丆場悢掕棟偵傛傝倗(倶)偼冇A(倶)偱妱傝愗傟傞丅
俠俙俽俤俀丗俙亗倣俤偺偲偒丆冇A(俙)佭倖A(俙)傛傝丆deg冇A亖俀
丂丂傛偭偰丆倗(倶)亖冇A(倶)倛(倶)亄倫倶亄倯偲偍偔偲丆
丂丂丂倗(俙)亖冇A(俙)倛(俙)亄倫俙亄倯俤
丂丂偙偺偲偒丆倗(俙)亖俷,冇A(俙)亖俷傛傝丆倫俙亄倯俤亖俷
丂丂偙偙偱倫亗侽偲偡傞偲丆俙亖倣俤偲側傞偺偱丆倫亖侽丆偝傜偵倯亖侽
丂丂傛偭偰丆倗(倶)偼冇A(倶)偱妱傝愗傟傞丅丂丂丂仩
Cor侾丏 俙偺屌桳懡崁幃倖A(倶)偼丆冇A(倶)偱妱傝愗傟傞丅
Cor俀丏 倖A(兩)亖侽佁冇A(兩)亖侽
pr)
 偼丆Cor侾傛傝惉棫
偼丆Cor侾傛傝惉棫
佀偵偮偄偰帵偡丅俙亖倣俤偺偲偒丆冇A(倶)亖倶亅倣丆倖A(倶)亖(倶亅倣)2傛傝惉棫
丂丂俙亗倣俤偺偲偒丆冇A(倶)亖倖A(倶) 傛傝惉棫偡傞丅丂丂丂仩
Remark俀亅俆丏 偙偺寢壥丆倖A(倶)亖侽偲冇A(倶)亖侽偺夝偼丆廳暋搙傪彍偄偰摍偟偄丅
Prop俀亅俇丏冇A(俙)亖(俙亅兛俤)(俙亅兝俤)亖俷 佀 俙偺屌桳抣偼丆兛丆兝偮傑傝丆俙偼丆兛丆兝傪屌桳抣偲偡傞峴楍偱偁傞丅
pr) 俙偺屌桳抣偼丆Prop俀亅係丏偺Cor俀丏傛傝丆兛丆兝偱偁傞偑丆deg冇A亖俀傛傝俙偼丆兛丆兝傪屌桳抣偲偡傞峴楍偱偁傞丅丂丂丂仩
埲忋偱弨旛偑廔椆偟偨偺偱丆杮榑偵擖傞丅
丂俀師偺惓曽峴楍俙偵懳偟偰丆佄1冇A(俙) 偐偮 deg冇A亝俀丂丂丂仚
(侾) 峴楍曽掱幃 俙2亄倠俙亄倢俤亖俷 偺夝偵偮偄偰
丂摿惈曽掱幃 倶2亄倠倶亄倢亖侽 偺俀偮偺夝傪兛丆兝偲偡傞偲偒兛亖兝乮廳夝乯傕娷傔偰峴楍曽掱幃
丂丂丂(俙亅兛俤)(俙亅兝俤)亖俷丂丂丂乮俀丏係乯
傪夝偗偽傛偄丅仚傛傝
俠俙俽俤侾丗deg冇A亖侾丆偮傑傝丆冇A(俙)亖俙亅兩俤亖俷偺偲偒丆俙亖兩俤傪乮俀丏係乯偵戙擖偟偰丆
丂丂丂(兩乕兛)(兩乕兝)俤亖俷丂丂兩亖兛丆兝
丂丂丂亪丂俙亖兛俤丆兝俤
俠俙俽俤俀丗deg冇A亖俀偺偲偒丆冇A(俙)偺堦堄惈傛傝
丂丂丂冇A(俙)亖(俙亅兛俤)(俙亅兝俤)亖俷丂丂丂乮俀丏俆乯
丂丂偙偙偱丆俙亅兛俤亗俷 偐偮 俙亅兝俤亗俷偱偁傞偐傜俙亅兛俤丆俙亅兝俤偼壜姺楇場巕偱偁傞丅
丂丂傛偭偰丆Prop俀亅俇丏傛傝丆俙偼兛丆兝傪屌桳抣偲偡傞峴楍偱偁傞丅
丂丂偙偺俙傪丆埲壓丆俙佭俙乮兛丆兝乯偲昞偡丅俙乮兛丆兝乯偺嬶懱揑側峔惉曽朄偵偮偄偰偼丆俇丏偱屻弎偡傞丅
埲忋傪尵偄姺偊傞偲丆
丂丂(鶣) 俙亖兛俤丆兝俤
丂丂(鶤) tr俙亖亅倠丆det俙亖倢傪傒偨偡擟堄偺俙
偲側傞偺偱丆朻摢偺寢壥偲堦抳偡傞丅
(俀) 俁師埲忋偺崅師曽掱幃 倗(俙)亖俷 偺夝偵偮偄偰
丂摿惈曽掱幃 倗(倶)亖侽 偺夝傪倶亖兛1丆兛2丆乧丆兛m偲偍偔偲丆廳夝傕娷傔偰
丂丂丂倗(俙)亖(俙亅兛1俤)(俙亅兛2俤)乧(俙亅兛m俤)亖俷丂丂丂仚傛傝
俠俙俽俤侾丗deg冇A亖侾偺偲偒丆俙亖兛1俤丆兛2俤丆乧丆兛m俤
俠俙俽俤俀丗deg冇A亖俀偺偲偒丆
丂丂丂冇A(俙)亖(俙亅兛i俤)(俙亅兛j俤)亖俷丆侾亝倝亗倞亝倣丂丂丂乮俀丏俇乯
丂丂偙偙偱丆俙亅兛i俤丆俙亅兛j俤偼丆偄偢傟傕亗俷傛傝壜姺楇場巕偱偁傞丅
丂丂俙亖俙乮兛i丆兛j乯
e丏g丏俀亅俈丂俙3亖俤傪夝偔偲丆(俙亅俤)(俙亅冎俤)(俙亅冎2俤)亖俷 傛傝
丂丂丂俙亖俤丆冎俤丆冎2俤丆俙乮侾丆冎乯丆俙乮侾丆冎2乯丆俙乮冎丆冎2乯
丂偙偺拞偱丆幚峴楍偼丆俙亖俤丆俙乮冎丆冎2乯 偺俀偮偱偁傞丅
丂埲忋偺俙傪値師惓曽峴楍偵奼挘偡傞偨傔偵丆師偺俁丏係丏偺弨旛傪偡傞丅
Prop俀亅侾丏俙偺屌桳抣偑丆兛1丆兛2丆乧丆兛n佀俠俫俤乮俁丏俁乯偑惉棫偡傞丅偮傑傝丆
丂丂丂倖A(俙)亖(俙亅兛1俤)(俙亅兛2俤)乧(俙亅兛n俤)亖俷
偑惉棫偡傞
丂偟偐偟丆偙偺媡偼惉棫偟側偄丅椺偊偽丆俙亖兛1俤偵偮偄偰丆乮俁丏俁乯偑惉棫偟偰偄傞偑丆偙偺俙偺屌桳抣偼兛1乮値廳夝乯偱偁傞丅
丂偦偙偱丆俙偺屌桳抣偑丆兛1丆兛2丆乧丆兛n偲側傞偨傔偺廫暘忦審傪峫嶡偡傞偨傔偵丆師偺嵟彫懡崁幃傪摫擖偡傞丅
丂埲壓丆値師惓曽峴楍俙偵偮偄偰丆偙偺嵟彫懡崁幃冇A(俙)偺懚嵼偲偦偺堦堄惈傪帵偡丅
Prop係亅俀丏乮嵟彫懡崁幃偺懚嵼乯
擟堄偺俙偵偮偄偰丆嵟彫懡崁幃冇A(俙)偑懚嵼偡傞
pr) 俠俫俤傛傝 倖A(俙)亖俷 偑惉棫偟偰偄傞偑丆偙傟偼値師幃偱偁傞丅侾師幃丂倗1(俙)亖俙亄倠1俤亖俷偐傜挷傋傟偽丆崅乆値夞偱倗k(俙)亖俷丂侾亝倠亝値偲側傞倗k(俙)傪摼傞丅
偙偺傛偆側倗k(俙)偺拞偱師悢偑嵟彫偺傕偺偑丆冇A(俙)偱偁傞丅丂丂丂仩
Prop係亅俁丏乮嵟彫懡崁幃偺堦堄惈乯
丂倗(俙)亖俷偲側傞擟堄偺懡崁幃倗(俙)偵懳偟偰丆倗(倶)偼冇A(倶)偱妱傝愗傟傞丅
pr) 倗(倶)亖冇A(倶)倛(倶)亄倰(倶)丆侽亝deg倰(倶)亙deg冇A(倶)偲偍偔偲丆
丂丂丂倗(俙)亖冇A(俙)倛(俙)亄倰(俙)
丂偙偙偱丆倗(俙)亖俷丆冇A(俙)亖俷傛傝丆倰(俙)亖俷 偙傟偼丆冇A(俙)偺嵟彫惈偵柕弬
丂丂丂亪 倰(倶)亖侽
丂傛偭偰丆倗(倶)偼冇A(倶)偱妱傝愗傟傞丅 丂丂丂仩
Cor侾丏 俙偺屌桳懡崁幃倖A(倶)偼丆冇A(倶)偱妱傝愗傟傞丅
Cor俀丏 倖A(兩)亖侽佁冇A(兩)亖侽
pr乯 偼丆Cor侾傛傝惉棫
偼丆Cor侾傛傝惉棫
佀偵偮偄偰帵偡丅俙偺擟堄偺屌桳抣傪兩偲偍偔偲丆佄倶亗侽丂倱丏倲丏俙倶亖兩倶
傛偭偰丆俙n倶亖兩n倶偺惉棫偲冇A偺慄宍惈傛傝 冇A(俙)倶亖冇A(兩)倶 偑惉棫丅
丂偙偙偱丆冇A(俙)亖俷傛傝 冇A(兩)倶亖侽丂丂丂亪丂冇A(兩)亖侽丂丂丂仩
Remark丏 偙偺Cor俀丏偺寢壥丆倖A(倶)亖侽偲冇A(倶)亖侽偺夝偼丆廳暋搙傪彍偄偰摍偟偄丅
e丏g丏係亅係丏師偺俁師偺奺惓曽峴楍偵偮偄偰丆偄偢傟傕俠俫俤偼丆倖(倶)亖(倶亅侾)3亖侽偱偁傞偑丆嵟彫懡崁幃偼丆慡偰堎側傞丅嬶懱揑偵偼丆
丂丂丂俙亖俤丗冇A(倶)亖倶亅侾
丂丂 丗冇B(倶)亖(倶亅侾)2丆
丗冇B(倶)亖(倶亅侾)2丆
丂 丂 丗冇C(倶)亖(倶亅侾)3
丗冇C(倶)亖(倶亅侾)3
丂埲忋偺嵟彫懡崁幃傪弨旛偡傞偲丆
Main Theorem係亅俆丏冇A(俙)亖(俙亅兛1俤)(俙亅兛2俤)乧(俙亅兛s俤)亖俷丂丂丂乮係丏侾乯
丂丂丂佀 俙偼丆兛1丆兛2丆乧丆兛s偐傜廳暋偟偰値屄揔摉偵慖傫偩慻兛1丆兛2丆乧丆兛n傪屌桳抣偲偡傞峴楍偱偁傞丅
偮傑傝丆俙亖俙(兛1丆兛2丆乧兛n)偱偁傞丅
丂扐偟丆兛1丆兛2丆乧丆兛s偐傜廳暋偟偰値屄傪慖傇偲偒丆斚傢偟偄偺偱昁梫偵墳偠偰屌桳抣偺斣崋偼帺桼偵晅偗懼偊偰丆兛1丆兛2丆乧丆兛n偲偡傞丅埲屻摨條偲偡傞丅
pr) 俙偺擟堄偺屌桳抣傪兩偲偡傞偲丆Prop係亅俁丏偺Cor俀丏傛傝丆侾亝佄倝亝倱丂s丏t丏丂兩亖兛i偱偁傞偑丆冇A偺嵟彫惈傛傝兛1丆兛2丆乧兛s偺偡傋偰偑俙偺屌桳抣偲側傞丅
丂傛偭偰丆俙偺屌桳抣偼丆廳暋搙傪彍偄偰兛1丆兛2丆乧丆兛s偱偁傞丅師偵丆値師惓曽峴楍俙偼廳暋搙傪娷傔値屄偺屌桳抣傪傕偮偺偱丆倱亝値傛傝俙偼丆兛1丆兛2丆乧丆兛s偐傜廳暋偟偰値屄揔摉偵慖傫偩慻兛1丆兛2丆乧丆兛n傪屌桳抣偲偡傞峴楍偱偁傞丅丂丂丂仩
丂偙偺寢壥傪丆師偺乮俆丏侾乯乮俆丏俀乯乮俆丏俁乯偱梡偄傞偙偲偵側傞丅
(侾) 峴楍曽掱幃 俙2亄倠俙亄倢俤亖俷 偺夝偵偮偄偰
丂摿惈曽掱幃 倶2亄倠倶亄倢亖侽 偺俀偮偺夝傪兛1丆兛2偲偡傞偲偒兛1亖兛2乮廳夝乯傕娷傔偰峴楍曽掱幃
丂丂丂(俙亅兛1俤)(俙亅兛2俤)亖俷
傪夝偗偽傛偄丅偙偙偱丆deg冇A亝俀傛傝丆
俠俙俽俤侾丗deg冇A亖侾偺偲偒丆亪俙亖兛1俤丆兛2俤
俠俙俽俤俀丗deg冇A亖俀偺偲偒丆冇A(俙)偺堦堄惈傛傝
丂丂丂冇A(俙)亖(俙亅兛1俤)(俙亅兛2俤)亖俷丂丂丂乮俆丏侾乯
兛1丆兛2偐傜廳暋偟偰値屄慖傫偱丆俙亖俙乮兛1丆兛2丆乧丆兛n乯
(俀) 俁師埲忋偐偮(値乕侾)師埲壓偺崅師曽掱幃 倗(俙)亖俷 偺夝偵偮偄偰
丂摿惈曽掱幃 倗(倶)亖侽 偺夝傪倶亖兛1丆兛2丆乧丆兛m (侾亝倣亝値)偲偍偔偲丆廳夝傕娷傔偰
丂丂丂倗(俙)亖(俙亅兛1俤)(俙亅兛2俤)乧(俙亅兛m俤)亖俷
偙偙偱丆deg冇A亝倣傛傝丆
俠俙俽俤侾丏deg冇A亖侾偺偲偒丆俙亖兛1俤丆兛2俤丆乧丆兛m俤
俠俙俽俤俀丏deg冇A亖倰偺偲偒丆兛1丆兛2丆乧丆兛m偐傜丆倰屄慖傫偱
丂丂丂冇A(俙)亖(俙亅兛i1俤)(俙亅兛i2俤)乧(俙亅兛ir俤)亖俷丂侾亝倝1亙倝2亙乧亙倝r亝倣丂丂丂乮俆丏俀乯
丂兛i1丆兛i2丆乧丆兛ir 偐傜廳暋偟偰値屄慖傫偱丆俙亖俙乮兛1丆兛2丆乧兛n乯
(俁) 値師埲忋偺崅師曽掱幃 倗(俙)亖俷 偺夝偵偮偄偰
丂摿惈曽掱幃 倗(倶)亖侽 偺夝傪丆廳夝傕娷傔偰倶亖兛1丆兛2丆乧丆兛m偲偍偔偲丆deg冇A亝値傛傝丆
俠俙俽俤侾丏deg冇A亖侾偺偲偒丆俙亖兛1俤丆兛2俤丆乧丆兛m俤
俠俙俽俤俀丏deg冇A亖倰偺偲偒丆兛1丆兛2丆乧丆兛m偐傜倰屄傪慖傫偱
丂丂冇A(俙)亖(俙亅兛i1俤)(俙亅兛i2俤)乧(俙亅兛ir俤)亖俷丂侾亝倝1亙倝2亙乧亙倝r亝値丂丂丂乮俆丏俁乯
丂丂兛i1丆兛i2丆乧丆兛ir偐傜廳暋偟偰値屄慖傫偱丆俙亖俙乮兛1丆兛2丆乧丆兛n乯
e丏g丏俆亅侾丏 俙2亅俀俙亄俤亖俷傪傒偨偡俁師偺惓曽峴楍俙傪媮傔傞偲丆
丂丂丂俙亖俤丆俙乮侾丆侾丆侾乯
e丏g丏俆亅俀丏俙4亖俤傪傒偨偡俁師偺惓曽峴楍俙傪媮傔傞偲丆
丂丂丂俙亖俤丆亅俤丆倝俤丆亅倝俤丆俙(兛丏兛丏兝)丆俙(兛丏兝丏兝)丆俙(兛丏兝丏兞)
丂丂偙偙偱丆兛丏兝丏兞偺慻偼丆亇侾丆亇倝偐傜慖傫偱丆侾俇捠傝
Prop俇亅侾丏擟堄偺惓懃峴楍俹偵懳偟偰丆俙偲俹-1俙俹偲偼偦偺屌桳抣偑堦抳偡傞丅
丂丂偮傑傝丆俙乣俛乮憡帡乯佀倖A(倶)亖倖B(倶)丆冇A(倶)亖冇B(倶) 偑惉棫偡傞丅
丂偙偺寢壥丆倶亖兛1丆兛2丆乧丆兛n 傪屌桳抣偲偡傞偁傞峴楍俙偼丆擟堄偺惓懃峴楍俹傪巊偭偰
丂丂丂 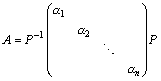
偲偟偰峔惉偡傟偽傛偄偑丆偙偺峔惉偵傛偭偰丆倶亖兛1丆兛2丆乧丆兛n 傪屌桳抣偲偡傞峴楍偑偡傋偰媮傑傞傢偗偱偼側偄丅斀椺偲偟偰丆 丆
丆 偵偮偄偰丆倖A(倶)亖倖B(倶)亖(倶亅侾)2偱偁傞偑丆俙乣俛偱側偄丅
偵偮偄偰丆倖A(倶)亖倖B(倶)亖(倶亅侾)2偱偁傞偑丆俙乣俛偱側偄丅
丂偮傑傝丆俹-1俙俹偵傛偭偰丆俛傪峔惉偡傞偙偲偼偱偒側偄丅
丂偦偙偱丆師偺傛偆偵懳妏壔乮昗弨壔乯傪梡偄傞丅
(侾) 俀師偺惓曽峴楍偺偲偒
Prop俇亅俀丏兛丆兝傪屌桳抣偲偡傞擟堄峴楍俙(亗倣俤)偵懳偟偰丆
丂嘥丏兛亗兝偺偲偒丆佄俹丗惓懃峴楍 倱丏倲丏 
丂嘦丏兛亖兝偺偲偒丆佄俹丗惓懃峴楍 倱丏倲丏 
pr乯 (偙偺徹柧偼偄傠偄傠側偲偙傠偱尵偄恠偔偝傟偰偄傞偑丆摿偵嘦丏偵偮偄偰丆倶1偲倶2偺楢棫曽掱幃乮俇丏侾乯偺夝偒曽傪岺晇偟偨偺偱丆懠偲斾傋偰捀偒偨偄乯
嘥丏偵偮偄偰丂俙倶1亖兛倶1丆俙倶2亖兝倶2 偲偍偔偲丆
丂丂丂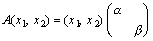
丂偙偙偱丆俹佭乮倶1丆倶2乯偲偍偔偲倶1丆倶2 偼堦師撈棫
乵佹if 偦偆偱側偄偲偡傞偲倶2亖倠倶1 傛傝俙(倠倶1)亖兝(倠倶1)丂丂丂兛倠倶1亖兝倠倶1
傛偭偰丆兛亖兝偲側傝柕弬両
傛偭偰丆俹偼惓懃偱丆 傛傝
傛傝 偑惉棫偡傞丅
偑惉棫偡傞丅
嘦丏偵偮偄偰丂傑偢丆廳夝忦審傛傝倖A(俙)亖冇A(俙)亖(俙亅兛俤)2亖俷
丂俹佭乮倶1丆倶2乯偲偍偔偲丆
丂丂丂 佁
佁 佁
佁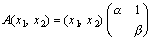 佁
佁 丂丂丂乮俇丆侾乯
丂丂丂乮俇丆侾乯
丂偙偺乮俇丏侾乯傪傒偨偡堦師撈棫側倶1丆倶2傪媮傔傟偽傛偄丅俙亅兛俤亗俷 傛傝 佄倶2 倱丏倲丏(俙亅兛俤)倶2亗侽
丂偙偺倶2偵懳偟偰戞俀幃傛傝倶1亖(俙亅兛俤)倶2 偲偡傞偲丆偙偺倶1偵偮偄偰(俙亅兛俤)2亖俷傛傝戞侾幃偑惉棫偟丆偐偮偙偺偲偒丆倶1偲倶2堦師撈棫
乵佹倠1倶1亄倠2倶2亖侽偲偍偔偲丆
丂丂丂倠1(俙亅兛俤)倶2亄倠2倶2亖侽丆倠1(俙亅兛俤)2倶2亄倠2(俙亅兛俤)倶2亖侽
丂偙偙偱丆(俙亅兛俤)2亖俷 偐偮 (俙亅兛俤)倶2亗侽 傛傝倠2亖侽丂偝傜偵倠1(俙亅兛俤)倶2亖侽傛傝倠1亖侽乶
丂傛偭偰丆俹亖乮倶1丆倶2乯偼惓懃偱丆
丂丂丂
Cor侾丏兛丆兝傪屌桳抣偲偡傞擟堄峴楍俙偼丆揔摉側惓懃峴楍俹傪巊偭偰丆
丂丂丂兛亗兝偺偲偒丆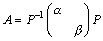 丆兛亖兝偺偲偒丆
丆兛亖兝偺偲偒丆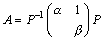
偲偐偗傞丅
e丏g丏俇亅俁丏俙2亅俀俙亄俤亖俷偺夝俙乮侾丆侾乯偼丆揔摉側惓懃峴楍俹傪巊偭偰丆 偲峔惉偱偒傞丅
偲峔惉偱偒傞丅
丂俙(侾丏侾)側傞堦偮偲偟偰椺偊偽丆 偺峔惉偼丆傑偢偦偺懳妏壔傪媮傔傞丅
偺峔惉偼丆傑偢偦偺懳妏壔傪媮傔傞丅
丂倶亖侾偑廳夝丆倖A(俙)亖冇A(俙)亖(俙亅俤)2亖俷丆(俙亅俤)倶2亗侽側傞倶2偲偟偰 偲偲傞偲丆
偲偲傞偲丆
丂丂丂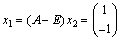
偙偺偲偒丆 偲偍偔偲
偲偍偔偲
丂傛偭偰丆偙偺俹傪梡偄偰丆
(俀) 値師偺惓曽峴楍偺偲偒
Prop俇亅係丏兛1丆兛2丆乧丆兛n傪屌桳抣偲偡傞擟堄偺峴楍俙偵懳偟偰
嘥丏冇A(倶)偑廳夝傪傕偨側偄佁俙偼丆懳妏壔偝傟傞
嘦丏冇A(倶)偑廳夝傪傕偮偲偒丆偦偺廳夝偺侾偮傪兛i偲偡傞偲丆俙偼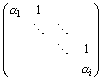 側傞嵶朎乮Jordan嵶朎乯峴楍傪偄偔偮偐暲傋偰偱偒傞峴楍偵憡帡乮Jordan偺昗弨宍乯
側傞嵶朎乮Jordan嵶朎乯峴楍傪偄偔偮偐暲傋偰偱偒傞峴楍偵憡帡乮Jordan偺昗弨宍乯
乮徹柧棯丆椺偊偽嵅晲堦榊挊亀慄宆戙悢妛亁傪嶲徠偝傟偨偄乯
e丏g丏俇亅俆丏 俙2亖俤傪傒偨偡俁師偺惓曽峴楍俙偱丆俙亖俤丆俙亖亅俤埲奜傪媮傔傞偲丆
丂丂丂冇A(俙)亖(俙亅俤)(俙亄俤)亖俷
偼廳夝傪傕偨側偄偺偱丆椺偊偽丆俙(侾丏侾丏亅侾)側傞擟堄偺俙偼丆揔摉側惓懃峴楍俹傪巊偭偰
丂丂丂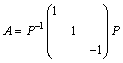
偲偟偰峔惉偱偒傞丅
e丏g丏俇亅俇丏(俙亅俤)2(俙亅俀俤)亖俷 傪傒偨偡俁師偺惓曽峴楍俙偼丆倶亖侾偑廳夝偵拲堄偟偰丆
deg冇A亖俀偺偲偒丆冇A(俙)亖(俙亅俤)2丆(俙亅俤)(俙亅俀俤) 傛傝椺偊偽丆
丂丂丂俙(侾丏侾丏侾)丆俙(侾丏俀丏俀)
側傞擟堄偺俙偼丆偦傟偧傟揔摉側惓懃峴楍俹傪巊偭偰丆
丂丂丂 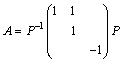 丆
丆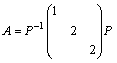
俹偲偟偰峔惉偱偒傞丅
deg冇A亖俁偺偲偒丆冇A(俙)亖(俙亅俤)2(俙亅俀俤) 傛傝俙(侾丏侾丏俀)側傞擟堄偺俙偼丆揔摉側惓懃峴楍俹傪巊偭偰丆
丂丂丂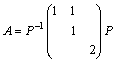
偲偟偰峔惉偱偒傞丅
丂俙(侾丏侾丏俀)側傞堦偮偲偟偰椺偊偽丆 偺峔惉偼丆Prop丏俇亅俁傛傝丆
偺峔惉偼丆Prop丏俇亅俁傛傝丆 偲偲傟偽傛偄丅
偲偲傟偽傛偄丅
e丏g丏俇亅俈丏(俙亅俤)4亖俷 傪傒偨偡係師偺惓曽峴楍俙偼丆倶亖侾偑廳夝偵拲堄偟偰丆
deg冇A亖俀偺偲偒丆冇A(俙)亖(俙亅俤)2 傛傝丆俙(侾丏侾丏侾丏侾)側傞擟堄偺俙偼丆揔摉側惓懃峴楍俹傪巊偭偰丆
丂丂丂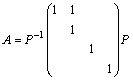 丆
丆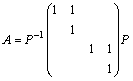
偲偟偰峔惉偱偒傞丅
Remark俇亅俉乮檖楇峴楍偺昗弨宍乯 偙偺e丏g丏俇亅俈丏偼丆俙亅俤佭俶 偲偍偔偲丆俶4亖俷丆 deg冇N亖俀 傛傝丆檖楇峴楍偺昗弨宍偐傜媮傔傞曽朄傕偁傞丅
Def俈亅侾丏乮壜姺楇場巕偺掕媊乯
丂俙偑壜姺楇場巕偲偼丆俷偱側偄俙偵懳偟偰 佄俛亗俷 倱丏倲丏俙俛亖俛俙亖俷
丂偙偺傛偆偵掕媊偡傞偲
Prop丏俈亅俀 俙偑壜姺楇場巕 佁 det俙亖侽
pr乯佀偼丆攚棟朄偐傜柧傜偐偩偑丆偙偺媡 傪嵟彫懡崁幃傪巊偭偰徹柧偡傞偲偲傕偵丆壜姺楇場巕俙偵懳偡傞俛偺峔憿傪柧傜偐偵偡傞丅
(侾) 俙偑俀師偺惓曽峴楍偺偲偒
det俙亖侽 傛傝丆俙偺屌桳抣傪丆侽丆兛 偲偍偔偲丆冇A(俙)亖俙(俙亅兛俤)亖俷
偙偙偱丆俛佭俙亅兛俤 偲偍偔偲丆冇A偺嵟彫惈傛傝 俛亗俷 倱丏倲丏俙俛亖俛俙亖俷
(俀) 俙偑値師惓曽峴楍偺偲偒
det俙亖侽 傛傝丆俙偺屌桳抣傪丆侽丆兛1丆兛2丆乧丆兛n-1 偲偍偔偲丆
丂丂倖A(俙)亖俙(俙亅兛1俤) 乧(俙亅兛n-1俤)
丂偙偙偱丆俙偺憡堎側傞屌桳抣傪丆夵傔偰丆侽丆兛1丆兛2丆乧丆兛s 偲偍偔偲丆deg冇A亖倰乮俀亝倰亝倱乯偺偲偒丆兛1丆兛2丆乧丆兛s偐傜倰亅侾屄傪慖傫偱丆夵傔偰兛1丆兛2丆乧丆兛r-1偲偍偔偲丆
丂丂丂冇A(俙)亖俙(俙亅兛1俤) 乧(俙亅兛r-1俤)亖俷
俛佭(俙亅兛1俤) 乧(俙亅兛r-1俤) 偲偍偔偲丆冇A偺嵟彫惈傛傝俛亗俷 倱丏倲丏俙俛亖俛俙亖俷
埲忋傛傝丆俙偼壜姺楇場巕偱偁傞丅丂丂丂仩
e丏g丏俈亅俁丏 偺偲偒丆冇A(俙)亖俙2(俙亅俤)亖俷
偺偲偒丆冇A(俙)亖俙2(俙亅俤)亖俷
丂傛偭偰丆俛佭俙(俙亅俤) 偲偍偗偽丆俙俛亖俛俙亖俷 偑惉棫偡傞丅
丂嵟屻偵丆偄偮傕儗億乕僩敪昞偺婡夛傪夣偔採嫙偟偰偔傟偨悢妛嫵堢幚慔尋媶夛丆摿偵栶堳偺曽乆丆傑偨丆偍朲偟偄拞挌擩側巜摫偟偰捀偄偨媑揷抦峴嫵庼偵丆姶幱怽偟忋偘丆寢傃偲偟偨偄丅