 数学における問題解決は、推理小説を読むようなものである。
数学における問題解決は、推理小説を読むようなものである。
 数学における問題解決は、推理小説を読むようなものである。
数学における問題解決は、推理小説を読むようなものである。
殺人事件が発生し(問題が提起され)、捜査の失敗が繰り返され(試行錯誤がなされ)、犯人が捕まる(解法が見つかる)。ところで、推理小説では、犯人の意外性としての面白さが必要不可欠な要素となっている。もちろん、この意外性は読者に対してのもので、小説の中の場面では、随所にその方向へと導く因子が配列されており、それに気がつけば、意外でも何でもない。当然の帰結なのである。
例えば、エルキュール・ポアロ(推理小説の女王、アガサ・クリスティ女史によって紹介された名探偵)は、事件の結末に意外性を感じたりはしない。ポアロ自身は事件が起こったとき、状況判断から、その独特の直観的思考で事件の真相の大筋を把握する。そして捜査段階でのちりばめられた小さな証拠を分析、統合し、犯人を追い詰めていく。やがて、その灰色の脳細胞が瞑想から醒めるとき、謎解きがなされ我々は犯人を知り、そこで意外性を感じるのである。
 では、それまでの間、読者はじっと我慢を強いられているかというと決してそうでもはない。読者もまた、同時に頭の中で事件を追っている。ポアロと並行して、捜査を進め、自分なりの結論をだす。だが、それ以上の真相をポアロから提示されるからこそインパクトがある。だから、小説をあとがきを先に読んでしまい、あらすじをあらかじめ知ってしまうと意外でもなんでもないことになる。急に興味は薄れ、こんな小説、何が面白いのだろうと首を傾げ、彼らにとってポアロはただのデブのお節介なおっさんに過ぎなくなるのだ。
では、それまでの間、読者はじっと我慢を強いられているかというと決してそうでもはない。読者もまた、同時に頭の中で事件を追っている。ポアロと並行して、捜査を進め、自分なりの結論をだす。だが、それ以上の真相をポアロから提示されるからこそインパクトがある。だから、小説をあとがきを先に読んでしまい、あらすじをあらかじめ知ってしまうと意外でもなんでもないことになる。急に興味は薄れ、こんな小説、何が面白いのだろうと首を傾げ、彼らにとってポアロはただのデブのお節介なおっさんに過ぎなくなるのだ。
こうして最初の一冊目の意外性から推理小説に取り憑かれた読者は、二冊目を読み出し、三冊目、四冊目と書棚には本が重ねられていくことになる。そして、そのうち読者は、ふと気がつく。自分を読書に駆り立てているのは、犯人探しの面白さよりもポアロという探偵に対する憧れと推理への挑戦であることに。
さて、話を戻そう。数学は、推理小説のようなものだといった。もちろん、数学という本が、推理小説という意味なのではない(といえるかもしれないが)。数学の問題が解かれる過程が推理小説に似ているということである。では、その問題解決の意外性はどこにあるかというと、例えば、初等幾何では、図形問題の補助線がそうである。突如として一本の線が図形を整理する。その分割の仕方が余りに鮮やかだから、惹かれるし、疎ましくもなる。この感情の対局的な立場は、補助線が引かれる前にどれだけ、図形を見ていた(読んでいた)かによるだろう。
そして、やはり推理小説の読者と同じく数学の解法においても、自分の解法とその深さに比例して、インパクトがあるのだ。たかだか一本の補助線が解答を導いていくだけのことなのに、解答者は「エレガント」という言葉の虜になってしまう。もっとエレガントな補助線が見つからないかと躍起になるのだ。
ところで、ここで一つ問題がある。では、数学の問題解法の過程においては、ポアロは誰なのだろう?。
それは数学を解く舞台が、生徒という解答者にとっては学校であることから明らかである。問題を提起し、灰色の脳細胞である黒板で推理を煮詰めた後、振り返りニヤッと笑い、自慢のワックスで固めた八の字形の口髭を撫でながら、南極ペンギンのように自信に溢れ反り返っているおっさんが勿論、ポアロである。
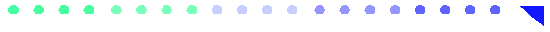
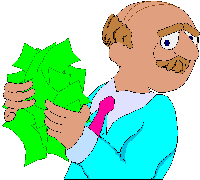 だけど、何より悲しいことは、余りに生徒が従順であることなのだ。いや、生活面に関してでは決してない。授業内容に関してのことである。従順であるから理解度が伺えない。だから喋りたくなる。喋ると、ただ黙々とノートを取っている彼らに、不安を覚えてきてまた喋る。彼らの目には、そんなポアロはどう映っているのだろう。
だけど、何より悲しいことは、余りに生徒が従順であることなのだ。いや、生活面に関してでは決してない。授業内容に関してのことである。従順であるから理解度が伺えない。だから喋りたくなる。喋ると、ただ黙々とノートを取っている彼らに、不安を覚えてきてまた喋る。彼らの目には、そんなポアロはどう映っているのだろう。
二次元コンプレックスという言葉があるんだそうな。これは、雑誌、ポスター、テレビといったような平面、すなわち二次元にしか興味を示さない若者の傾向をいっている。実際、彼らの日常生活は、二次元文化に溢れている。ファミコンでは、主人公に自分を投影させ、生死を賭けたゲームに興じている。カラオケでは、ビデオを見ながら、歌手の歌い方を真似ることが、歌うことと信じている。レンタルビデオを観ながら、ドラマの感動を自分の人生とオーバーラップさせようとする。そんら彼らだから、ひょっとしたら授業も二次元のものと見ているのかもしれない。
ポアロは考える。自分と彼らを隔てているのは、10センチほどしかない教壇の高さである。この境目に、スクリーンの幕が降りているのではないかと。そう思えばすべて納得がいく。自分は銀幕の中の俳優で、お定まりの陳腐な演技を時間とともに始める。彼らにとってそれは目の前の二次元上の出来事だから、参加する必要だってありはしない。最近はやりのマニュアルビデオのようにほっとけばみんな喋ってくれると思っている。15分ごとにコマーシャルで息抜きをしなければ集中できない彼らに、サービスで、冗談でも喋ってやろうかとさえ思う。
でも、とまた疑問が鎌首をもたげる。銀幕の内側にいるのは、なぜ、自分の方なのだろうか。これだけ悩んでいる自分が、どうして虚像でなければいけないのだろう。二次元とは漫画のように動かないものだ、と思っている古い世代の彼には、反応が、表情が読み取れない生徒のほうが、スクリーン上の虚像のように思えるのだ。いっそのこと、映画「カイロの紫のバラ」の主人公のように、スクリーンの向こう側の世界に飛び降りることができたら思うのだが、10センチの教壇の高さは、彼にとっては10メートルの崖の高さに思えるのだ。
こんな風に気が滅入ったとき、きまってポアロは昔読んだ本を思いだす。その題名は、「さあ数学しよう」 〜MATH!〜(岩波書店)。なんだ、題名が日本語になってないじゃないか、とブツブツと文句をいいながらも読み、いつのまにか、とてもこの日本語が好きになってしまった本である。著者は、S.ラング。アメリカのエール大学の数学教授。内容は、カナダとフランスのハイスクールで彼が講義した数学の記録である。πr2という公式でしか円周率を知らない15歳の若者らに、ラング氏は、僅か1時間ほどで、対話を通して、πのイメージを与えてしまう。
ラング氏の教授法は、「分からない生徒」の疑問を引き出すことから始める。そして、その考え方が間違っていても決して否定したりはしない。その疑問から引き出せるものを大切にしながら展開していき、徐々に生徒の頭の中に、3.14でも円周率という言葉でもない、πのイメージを作っていく。
初めて読んで、ポアロは感動した。何度も何度も読み返して、何度も何度も感動した。「数学する対話」(日本語が変になってしまった)が必要なんだと一人で納得した。そして思った。たぶん、ラング氏の教授法は、『才を編む』ことなんだろう。生徒の持っている才能を、優しく引きだし、丁寧に、丁寧に編んでいく。そして、それはやがて誰が見ても、円というタペストリーに織り上がっていくのである。
この本はポアロのバイブルとなった。
だが、現実は甘くない。直面するいまの状況は、バイブルでは救えない。なぜなら彼はポアロであって、ラング氏ではないのだから。ラング氏ほどの豊富な数学知識はないし、いつも直観的思考力だけで困難を乗り越えてきた。だから、今度だってと思うのだ。
だが、まてよ。『才を編む』、才能を編むなんてことはできないにしても、引き出すことぐらいはできないのだろうか。ふと、最近読んだ雑誌の内容が、彼の頭の中を駆け巡った。
右脳の働きというのが最近、脚光を浴びてきている。右脳とはイメージ脳である。非言語機能ともいわれ、直感力、感性といった創造的なひらめきに関与している。これに対して、左脳は言語機能であり、論理的、分析的な機能をもつ。いま、なぜ右脳が問題にされるのかというと、知識、論理といった科学至上主義が息詰まりをみせているからなのである。学校教育でも、偏差値とか、内申点といった言語機能の獲得が目標とされ、公式を覚えることが最優先であり、理解は二の次なのである。でも、これではコンピュータとその思考回路は変わらないことになる。それが社会現象として白けた冷たい目を持つ世代を生み出してしまった。この偏った言語機能に歯止めをかける為に感性としての右脳の必要性が叫ばれているのだ。
いま目の前で、機械のように板書を続ける彼らは、明らかに左脳で授業を受けているのである。だから、何とか右脳を目覚めさせてやればいいのだ。その右脳のもつひらめき、感性こそが、問題解決の喜びにつながり、従順な彼らも、疑問に対して素直な反応ができるようになるだろう。さあ、右脳をこちょこちょって、刺激してやるんだ。そうすれば、そうすれば、……でも、どうやって?
雑誌の受け売りを信用したのが間違いだったと後悔するポアロであった。右脳の理論は言語機能の左脳を使ってうまく書かれてはいるけれど、実践に移すだけのものがないのだ。これじゃ、机上の空論に過ぎない。だいたいよく考えると、聖書の中にも「はじめにロゴスありき」って言葉がある。論理こそ最初であるということだからこの頃から既に、言語機能偏重はあったってことだ。だから、その後哲学者が、パトスって情の必要性を唱えていたんじゃないか。そんな大昔の議論を再び今また大脳生理学者は蒸返している。これじゃ、いつまでたっても、いたちごっこじゃないか。
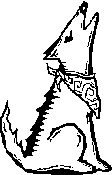 可哀相なのは、その研究のために犠牲になった多くのモルモット達だ。例えば、パブロフの犬。彼は、メトロノームの音を聴いただけで唾液を流すだらしのない犬にされてしまった。だいたい、パブロフの犬って言い方は、犬に失礼じゃないか。パブロフのポチとか、シロとかいいようがあったろう。それに較べると、初めて宇宙にいった犬、ライカ犬。彼が宇宙から見た地球は、素晴らしいものだったろうなあ。人間にさえ見ることのできなかった光景を、彼はみた。彼はどういう気持ちで見ていたのだろう?
可哀相なのは、その研究のために犠牲になった多くのモルモット達だ。例えば、パブロフの犬。彼は、メトロノームの音を聴いただけで唾液を流すだらしのない犬にされてしまった。だいたい、パブロフの犬って言い方は、犬に失礼じゃないか。パブロフのポチとか、シロとかいいようがあったろう。それに較べると、初めて宇宙にいった犬、ライカ犬。彼が宇宙から見た地球は、素晴らしいものだったろうなあ。人間にさえ見ることのできなかった光景を、彼はみた。彼はどういう気持ちで見ていたのだろう?
そこで、ふっとポアロの右脳は閃いた。
犬の立場で考えると、地球の光景なんてどうでもいいことだったかもしれない。どうしてライカ犬の方がパブロフの犬より幸せだったと言い切れるだろう。少なくとも、三度のおまんまが与えられていた分だけ、パブロフの犬の方が幸せだったかもしれない。そう、相手の気持ちになって考えてやるということを、自分は忘れていたんだ。生徒のことにしたってそうだ。いつだって、生徒と距離をおいて分かろうとしていた。自分が分かっただけでは駄目なんだ。自分で分かったことが生徒も分からなきゃ駄目なんだ。お互いが「分かりあえる」ってことが大事なんだ。じゃあ、その為には?。目を上げると、無表情の中に不安が見え隠れしている目達がポアロの方を見ていた。
反り返った体を少し前屈みにして、ポアロは、僅か10センチの教壇を、ひょいっと飛び降りた。