第2章 二つの知の間に
―――――― カルネアデスの舟板
「先生、カルネアデスの舟板知ってますか?」。
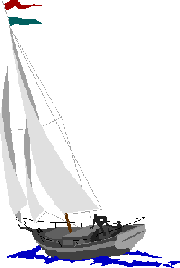 ドキッとしてポアロは瞑想から現実に引き戻された。振り返ると、パイプの煙でぼやけた中から相手の心の奥底を覗き込むような鋭い視線を向けているホームズ先生がいた。ポアロはこの先生が好きではない。彼の言葉は丁寧であるがその端々、イントネーションに相手を値踏みし、見下すような慇懃無礼なところがある。カネナイデスの舟板?、「舟板について知ってますか」じゃなく「舟板知ってますか」と尋ねることに、答えられるなら答えてみろという彼特有の挑戦の匂いがする。残念ながらポアロはその舟板について知らなかった。だが、そのことを言う前に、ホームズは先を続けていた。「これは刑法の緊急避難の問題なのですが、船が難破し投げ出された2人が1人分の重さにしか耐えられない板にしがみつこうと争って一人が相手を溺れさせてしまった場合、その人は罪を問われず無罪とみなされるというんです。でも実際に先生が二人のうちの一人であったとしたら、先生はどうしますか。」ポアロは身構えた。自分が死んでも助かっても悔いの残る選択じゃないか。カネなんとかの舟板の質問の背後にあるホームズの根深い思惑を読み取ろうとしたが、相変わらず彼はパイプの煙をくゆらせペダンチックな態度でこちらの反応を楽しんでいる様子である。難破したもう一人がホームズならそのときの決断は決まっているのにと思ったが、ポアロはそのカンなんとかの舟板の回答の後のホームズの猛撃を予想して逃げ腰になっていた。「いや、いまはちょっと時間がなくて。生徒を待たせているものですから。」まとわりついているホームズの視線を断ち切るように出席簿と教科書をもってポアロは廊下にでていた。
ドキッとしてポアロは瞑想から現実に引き戻された。振り返ると、パイプの煙でぼやけた中から相手の心の奥底を覗き込むような鋭い視線を向けているホームズ先生がいた。ポアロはこの先生が好きではない。彼の言葉は丁寧であるがその端々、イントネーションに相手を値踏みし、見下すような慇懃無礼なところがある。カネナイデスの舟板?、「舟板について知ってますか」じゃなく「舟板知ってますか」と尋ねることに、答えられるなら答えてみろという彼特有の挑戦の匂いがする。残念ながらポアロはその舟板について知らなかった。だが、そのことを言う前に、ホームズは先を続けていた。「これは刑法の緊急避難の問題なのですが、船が難破し投げ出された2人が1人分の重さにしか耐えられない板にしがみつこうと争って一人が相手を溺れさせてしまった場合、その人は罪を問われず無罪とみなされるというんです。でも実際に先生が二人のうちの一人であったとしたら、先生はどうしますか。」ポアロは身構えた。自分が死んでも助かっても悔いの残る選択じゃないか。カネなんとかの舟板の質問の背後にあるホームズの根深い思惑を読み取ろうとしたが、相変わらず彼はパイプの煙をくゆらせペダンチックな態度でこちらの反応を楽しんでいる様子である。難破したもう一人がホームズならそのときの決断は決まっているのにと思ったが、ポアロはそのカンなんとかの舟板の回答の後のホームズの猛撃を予想して逃げ腰になっていた。「いや、いまはちょっと時間がなくて。生徒を待たせているものですから。」まとわりついているホームズの視線を断ち切るように出席簿と教科書をもってポアロは廊下にでていた。
情けなかった。ホームズの問いに答えられなかったのはもちろんだが、普段のポアロなら、その灰色の脳細胞が本能的にその後の対処すべきパターンを用意してくれていた。いまの彼にはその閃き、余裕が失われていることが情けなかった。実は、それが彼が瞑想に耽っていた理由なのである。
ポアロにとって10センチの教壇の高さはすでにない。いつでもひょいと教壇を降り生徒の中に入っていけるようになっていた。講義の途中、くぐもった声での質問があると駆け降り納得するまで教えた。それまでは無表情に思えていた生徒の目はいまは様々な言葉で話し掛けてきた。「見るという字は目に足がついている」とはよくいったものである。彼は生徒の質問に答えられる自分を誇らしく思い、ホームズのようにけっして自己満足で終わっていないという自負があった。だからどんな質問にも答えられるように、教材研究にはいままで以上に力をいれ、彼の書棚は、ポントリャーギンの連続群論のような専門誌の前を、赤塚不二夫の「おもしろ数学教室」とか、秋山仁の「数学トレーニング」といった数学解説書が堂々と占居するようになった。灰色の脳細胞は問題を分析する前に、生徒の理解度を把握することを優先せさ、ワックスで固めた八の字型の口髭アンテナは常に生徒に向けられいる。自分と生徒との距離は確かに短くなったと思った。自分が変わったことで生徒も変わっていく様を彼は嬉しそうに見守り教育者としての法悦に浸っていた。
そのポアロを奈落の底に突き落としたのが全校一斉数学推理コンテスト(彼以外の先生は、定期考査といっている)。彼のクラスは学年最下位だったのである。
いま「編みかけた才」は、誰かに毛糸の先を引っ張られているようにほどけ、思考はもつれていった。自問自答しても答えは見つからない。彼自身が才を編むために構築した教育理論はそれほど完璧なものだったはずなのだ。10センチの教壇の崖を飛び降りてからポアロは生徒との対話を限定された時間内で効率的にするために「三段教授法」<Three Step Teaching;略してTST>なるものを考案した。
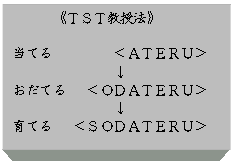
分かり合うためにできるだけ多くの生徒に「当てる」ことで、生徒と疑問や悩みを共有し、理解したら「おだてる」ことで生徒を褒めて成就感をもたせ、生徒が意欲的に学習するように「育てる」。こうして、その時間のテーマに段階を経て近づけるというものである。「誰でも簡単にできるんだよ」ということを強調することで、ピグマリオン効果<結果が期待を作り上げてしまう効果>を狙ったのである。生真面目なポアロにしてはローマ字のスペル変化との対応が妙に気に入っていた。TSTを授業の中に取り入れてから、教育効果は上がったとポアロは確信している。生徒の喰いつきが違うのである。さ迷える小羊<ストレイシープ>の眼は、草を食む平和な小羊の目に変わっていった。その成果が数字ででてくることを期待していただけに推理コンテストの敗北はショックだった。実は、ホームズに声をかけられたとき、瞑想というより自責の念で沈みこみ、それでも必死に敗因を分析しようとしていたのだ。
迫り出した腹が邪魔して見えるはずもない床に眼を落とし、ブツブツと独り言を呟きながらポアロは教室に入っていった。
「起立!。礼!」。だらしなく立ち、首をコクッと傾げる子供達。いつもの光景。チョークの粉が白く引き伸ばされ白粉をしたようないつもの黒板。このいつもの繰り返しがとても新鮮に思えたこともある。だが情熱は急速に冷めつつあった。しらけていく感情を制御できない自分に苛立ち、打開策を見いだせない脳細胞を責めた。
ポアロは重たそうにチョークをもち、黒板に「ロバの問題」と書いた。振り返る。86個の目が彼に注がれている。その目も以前ほどの輝きは失せている。明らかにポアロの感情の冷気は生徒達も冷やしているのだ。ポアロは視線から逃れるように目を空に泳がした。そして、おもむろに説明を始めた。
「今日は、ロバの問題について考えてみよう。ロバって、人の名前じゃないよ。あのパカパカ歩く馬の親戚のことだよ。」。……はずした。笑いがとれるところなのに教室内は静まりかえっている。外したときほど惨めなことはない。慌てて取り繕うように彼は黒板に図を書き始めた。
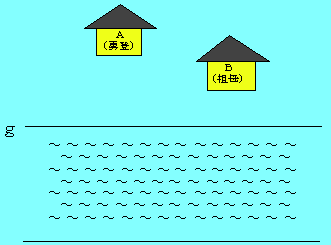 気持ちを落ち着かせながら書いていく。もう冗談は言うまいと心に決めて、説明を続ける。「図中、A地点にいる勇登君が、ロバを連れて、川に水を汲みにいき、ポリタンクに入れた水をロバの背に乗せてB地点にいるおばあちゃんのところまで届けたい。どこの川岸で水を汲むのがいちばんいいだろうか。」
気持ちを落ち着かせながら書いていく。もう冗談は言うまいと心に決めて、説明を続ける。「図中、A地点にいる勇登君が、ロバを連れて、川に水を汲みにいき、ポリタンクに入れた水をロバの背に乗せてB地点にいるおばあちゃんのところまで届けたい。どこの川岸で水を汲むのがいちばんいいだろうか。」
相変わらず、ことりとも音がしない。「じゃあ図に適当な経路を書き込んでごらん」。やっと、もぞもぞと生徒は動きだす。ポアロを机間交流(巡視)しながら生徒の推理を分析し始めた。点Aから直線gに垂線を下ろしている生徒がいる。ふむ、gへの最短距離を考えたのだろうが、その後のことを考慮にいれていない。次に、光咲の前にいくと、彼女は点Bからgに垂線を引いている。彼女も同じだ。水を汲む前のことを考えていない。だが大半の生徒はもっと悪い。鉛筆を器用に人差し指の回りに回転させ、頬杖をついて目をボーッと図に落としている。こういう傾向は最近多くなった。生徒の学習意欲が低下したのではなく、ポアロは自分に対する期待が高くなったのだと思っている。
フランスの科学者モーペルティユが提唱した「最小作用の原理」<俗称モーペルティユの原理>というのがある。自然界は、最小の努力で最大の効果をあげようとするもので、無駄なことは極力さける傾向にある。簡単にいえば、自然はラクをしたがるということである。そしてそれは生徒にもいえることだ。生徒が考えようとしないのは、1分もたてば解答が用意されるからなのだ。ポアロがTSTを通して説明することを理解すればよいわけで、知恵を絞ることに無駄な労力は使いたくはない。彼らは問題状況を把握しようとしているだけで、推理しようとしてはいないのだ。その心情を頭脳明晰なポアロは薄々気づいてはいた。1時間の中で集中力をどれだけ維持できるかというのは難しい。ポアロは自分の解説に対して集中することを第一義と考えたから、多少のことは無視した。「最小作用の原理」をポアロは、自然は平均化(調和化)する傾向にあるものだと解釈している。自然界で目立った行動は自然淘汰の餌食となるものである。平均化しながら自然はテンションを高めていくべきであり、生徒も強調歩調の中で理解しなければならない。そのためのTSTなのである。
「さあ、それではもう一度考えてみようか」。ポアロは何人かの生徒に「当て」、その誤りを正した。発想としては50%正しいことを褒め「おだてて」、ではどうすれば解決できるか「育てる」推理を始めた。
「直線gに関して点Aの対象点A′をとり、A′Bとgの交点をPとする………。
………よって、この点Pが勇登が水を汲む場所である。」
縷々盛らす事なく説明し、ポアロは推理を終え事件は大円団を迎えた。ポアロは満足気に回想というまとめを話しだす。そのとき、「先生、でもそれおかしい。」。声の方向に目を向けると光咲が口を尖らして抗議していた。
光咲は数学が得意ではない。だからポアロはできるだけ「当てて」、彼女の誤りを正し、推理の道筋から外れることのないよういつも配慮していた。今日の問題では、川までの最短距離を大半の生徒は点Aから考えたのに対し、彼女は点Bから引いていた。その誤りは点Aに対して正せば十分であるとの判断をポアロはしたのである。したがって、そんなことも理解できないかとポアロは失望感と同時にやや気色ばんだ。
「光咲、君の誤りは先程説明した、点Aから川の最短距離の発想と同じなのだよ。そのことが分からなかったのかな。」
もう、推理は終わったのだぞ。この後にトリックなどは用意されてはいない。ポアロは憤慨していたが、光咲は納得していない様子だ。
「先生、違うの。わたしが言いたいのは、ロバは背中にポリタンクを背負っているんだから、汲んだ後の距離が短いほどロバにとってはいいんじゃないのかいうことなの。」
……。ポアロは絶句した。そして、自分の過ちにやっと気づいた。
ポアロは、どこの川岸で汲むといちばんいいかと問いかけたのであって、それは必ずしも最短経路を要求することではない。時間の要素を加味すれば、最短時間でもいいわけで、さらにそれにポリタンクを背負ったことで、歩く時間が遅くなるロバのこと、その肉体的な疲労までも考慮すれば光咲の解答が間違いであるとはいえないのである。明らかに問題提示としては不備があったということになる。だが、ポアロが悟った過ちとはそれだけではない。光咲の推理は、ポアロの思考領域の外側にあったものであり、マニュアル論理化された彼の思考には、暖かく新鮮なものに映った。彼は「個々の才能の深遠さ」に触れ、そして驚愕したのである。
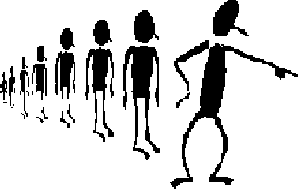 ポアロは生徒の習熟度をいつも自分の尺度で判断していたと思う。彼が「当てる」ときは、いつも、彼の推理から逸脱しないように生徒の知恵を方向修正してきた。彼が「おだてる」とき、それは彼の推理に近づいたことへの賛辞である。そして、彼が「育てる」ことは、思考がポアロのクローンとなるように知識を「刷り込む」ことであった。
ポアロは生徒の習熟度をいつも自分の尺度で判断していたと思う。彼が「当てる」ときは、いつも、彼の推理から逸脱しないように生徒の知恵を方向修正してきた。彼が「おだてる」とき、それは彼の推理に近づいたことへの賛辞である。そして、彼が「育てる」ことは、思考がポアロのクローンとなるように知識を「刷り込む」ことであった。
生徒が考えることを放棄したのは、理解しているからではない。理解する必要がなかったからなのだ。たぶん、生徒は授業の中で理解したと思っていることを自分で咀嚼して消化しようとはしなかったはずだ。だから翌日になったらもう忘れてしまっている。ポアロの授業は続きのない単発ドラマなのである。
いったい、ポアロが編ませようとしたタペストリーは何だったのだろう。ポアロが図案を描いて、生徒がそれを織る。大量生産で作られた、下町の路地で1枚1,000円で売られているちっぽけなまがい物。「才を編む」なんてこちらの思い上がりであった。どんなタペストリーが編み上がるなんてきっと本人でさえ分からない。それだけ無限の可能性を秘めているものなのだ。
ポアロのTSTの失敗もそこにある。「当てる」とき、それは知識をポアロの知っているものに修正してやるべきであって、知恵まで修正すべきではないのだ。知識は鞭、知恵はアメ。知識は説得すること。知恵は納得させること。「モーペルティユのの原理」はそのバランスの中でラクをするのである。だが、ポアロは生徒の知恵まで知識に変えようとしていたのである。
全校数学推理コンテスト最下位。それは、生徒達のポアロへの無言の抵抗であったのだ(もちろん生徒達はそんなことは意識してないだろうが)。
そんなことも気づかないで、ピョンピョンと教壇を飛び降りていた自分をポアロはピエロだと思った。おおーっ!。ポアロとピエロ、なんと似た響きなのだろう。思い上りという感情で膨らんだ風船玉に乗って一人おどけていたピエロ。これじゃホームズと変わらないじゃないか。
生徒達はみんな、ポアロの言葉を待っていた。真摯でクリアな光咲の眼差しがとても眩しく、尊く思えた。一呼吸おいて、ポアロは喋りだした。
そうだね。光咲くん。先生、間違っていたみたいだ。問題を訂正しよう。」
ポアロは黒板の問題を「最も短い経路を求めよ。」と書き直し、さらに「ロバの問題」のロバを消して、ミサキと書いた。
「今日から最短経路の問題を、ミサキの問題と呼ぶことにしましょう。みんなミサキのこと、忘れないようにしよう。」。ポアロは自分にいい聞かせるようにいったのだが、生徒達はクスクスしだし、光咲も照れ笑いしていた。そして、授業終了のベルが鳴った。
「起立!、礼!」
ポアロは、深々と生徒に向かって頭を垂れた。
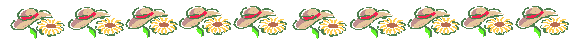
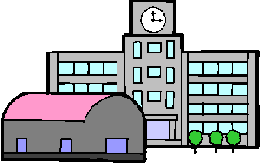 職員室に戻ると授業のなかったホームズがマープル女史に熱心に話しかけている。パイプの煙は紫色の毒気となって、ホームズの言葉をよりいっそう嫌味なものとしているのだろうか、マープル先生の表情は苦渋に歪んでいた。ポアロは、スタスタとホームズに歩みより、マープル先生との間に入って言った。
職員室に戻ると授業のなかったホームズがマープル女史に熱心に話しかけている。パイプの煙は紫色の毒気となって、ホームズの言葉をよりいっそう嫌味なものとしているのだろうか、マープル先生の表情は苦渋に歪んでいた。ポアロは、スタスタとホームズに歩みより、マープル先生との間に入って言った。
「先生、先程の舟板の質問分かりましたよ」。
会話を邪魔されたホームズは、細めた目に、意地悪い光を湛えながら、吐き捨てるようにいった。
「ほう!、そうですか?。で、どうします。自分が助かりますか。それとも相手を助けますか」
ポアロの灰色の脳細胞が目の前の敵に向かって急速に回転し始めた。
「先生、そういうふうに制限された解答の中で考えるべきではないのですよ。最善の努力をすることを忘れちゃいけないのです。ふたりが替わり
替わるに舟板につかまって、救助がくるまで待ってもいいんじゃないでしょうか。」
呆気にとられたホームズを尻目に、ポアロは口髭ほどに開いた笑みを、ミス・マープルにおくった。
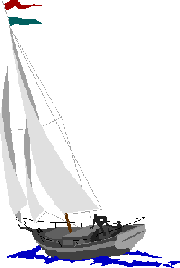 ドキッとしてポアロは瞑想から現実に引き戻された。振り返ると、パイプの煙でぼやけた中から相手の心の奥底を覗き込むような鋭い視線を向けているホームズ先生がいた。ポアロはこの先生が好きではない。彼の言葉は丁寧であるがその端々、イントネーションに相手を値踏みし、見下すような慇懃無礼なところがある。カネナイデスの舟板?、「舟板について知ってますか」じゃなく「舟板知ってますか」と尋ねることに、答えられるなら答えてみろという彼特有の挑戦の匂いがする。残念ながらポアロはその舟板について知らなかった。だが、そのことを言う前に、ホームズは先を続けていた。「これは刑法の緊急避難の問題なのですが、船が難破し投げ出された2人が1人分の重さにしか耐えられない板にしがみつこうと争って一人が相手を溺れさせてしまった場合、その人は罪を問われず無罪とみなされるというんです。でも実際に先生が二人のうちの一人であったとしたら、先生はどうしますか。」ポアロは身構えた。自分が死んでも助かっても悔いの残る選択じゃないか。カネなんとかの舟板の質問の背後にあるホームズの根深い思惑を読み取ろうとしたが、相変わらず彼はパイプの煙をくゆらせペダンチックな態度でこちらの反応を楽しんでいる様子である。難破したもう一人がホームズならそのときの決断は決まっているのにと思ったが、ポアロはそのカンなんとかの舟板の回答の後のホームズの猛撃を予想して逃げ腰になっていた。「いや、いまはちょっと時間がなくて。生徒を待たせているものですから。」まとわりついているホームズの視線を断ち切るように出席簿と教科書をもってポアロは廊下にでていた。
ドキッとしてポアロは瞑想から現実に引き戻された。振り返ると、パイプの煙でぼやけた中から相手の心の奥底を覗き込むような鋭い視線を向けているホームズ先生がいた。ポアロはこの先生が好きではない。彼の言葉は丁寧であるがその端々、イントネーションに相手を値踏みし、見下すような慇懃無礼なところがある。カネナイデスの舟板?、「舟板について知ってますか」じゃなく「舟板知ってますか」と尋ねることに、答えられるなら答えてみろという彼特有の挑戦の匂いがする。残念ながらポアロはその舟板について知らなかった。だが、そのことを言う前に、ホームズは先を続けていた。「これは刑法の緊急避難の問題なのですが、船が難破し投げ出された2人が1人分の重さにしか耐えられない板にしがみつこうと争って一人が相手を溺れさせてしまった場合、その人は罪を問われず無罪とみなされるというんです。でも実際に先生が二人のうちの一人であったとしたら、先生はどうしますか。」ポアロは身構えた。自分が死んでも助かっても悔いの残る選択じゃないか。カネなんとかの舟板の質問の背後にあるホームズの根深い思惑を読み取ろうとしたが、相変わらず彼はパイプの煙をくゆらせペダンチックな態度でこちらの反応を楽しんでいる様子である。難破したもう一人がホームズならそのときの決断は決まっているのにと思ったが、ポアロはそのカンなんとかの舟板の回答の後のホームズの猛撃を予想して逃げ腰になっていた。「いや、いまはちょっと時間がなくて。生徒を待たせているものですから。」まとわりついているホームズの視線を断ち切るように出席簿と教科書をもってポアロは廊下にでていた。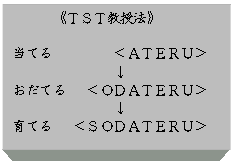
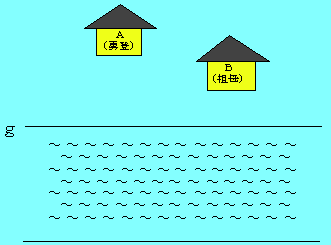 気持ちを落ち着かせながら書いていく。もう冗談は言うまいと心に決めて、説明を続ける。「図中、A地点にいる勇登君が、ロバを連れて、川に水を汲みにいき、ポリタンクに入れた水をロバの背に乗せてB地点にいるおばあちゃんのところまで届けたい。どこの川岸で水を汲むのがいちばんいいだろうか。」
気持ちを落ち着かせながら書いていく。もう冗談は言うまいと心に決めて、説明を続ける。「図中、A地点にいる勇登君が、ロバを連れて、川に水を汲みにいき、ポリタンクに入れた水をロバの背に乗せてB地点にいるおばあちゃんのところまで届けたい。どこの川岸で水を汲むのがいちばんいいだろうか。」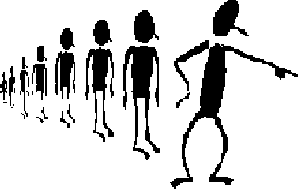 ポアロは生徒の習熟度をいつも自分の尺度で判断していたと思う。彼が「当てる」ときは、いつも、彼の推理から逸脱しないように生徒の知恵を方向修正してきた。彼が「おだてる」とき、それは彼の推理に近づいたことへの賛辞である。そして、彼が「育てる」ことは、思考がポアロのクローンとなるように知識を「刷り込む」ことであった。
ポアロは生徒の習熟度をいつも自分の尺度で判断していたと思う。彼が「当てる」ときは、いつも、彼の推理から逸脱しないように生徒の知恵を方向修正してきた。彼が「おだてる」とき、それは彼の推理に近づいたことへの賛辞である。そして、彼が「育てる」ことは、思考がポアロのクローンとなるように知識を「刷り込む」ことであった。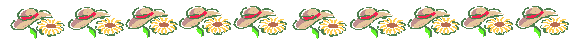
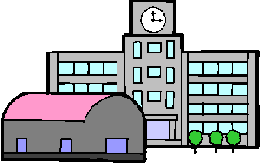 職員室に戻ると授業のなかったホームズがマープル女史に熱心に話しかけている。パイプの煙は紫色の毒気となって、ホームズの言葉をよりいっそう嫌味なものとしているのだろうか、マープル先生の表情は苦渋に歪んでいた。ポアロは、スタスタとホームズに歩みより、マープル先生との間に入って言った。
職員室に戻ると授業のなかったホームズがマープル女史に熱心に話しかけている。パイプの煙は紫色の毒気となって、ホームズの言葉をよりいっそう嫌味なものとしているのだろうか、マープル先生の表情は苦渋に歪んでいた。ポアロは、スタスタとホームズに歩みより、マープル先生との間に入って言った。